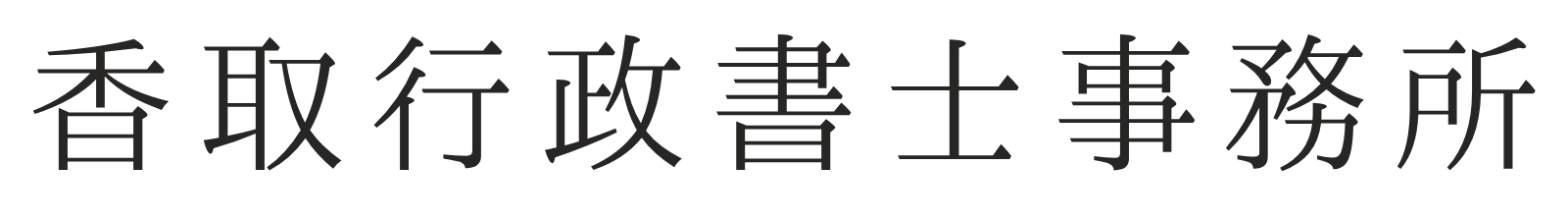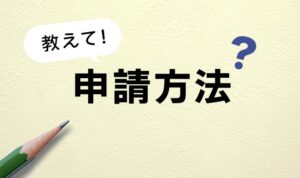営業所とは
営業所とは、古物営業を行う拠点となる場所をいい、その本拠となる営業所を「主たる営業所」といいます。
古物商の営業の制限
古物営業法は、古物商は営業所又は取引の相手方の営業所、住所、居所以外の場所で古物を買い受け若しくは交換、または委託を受けて売買し、交換をする場合には、古物商以外の者から古物を受け取ってはならないと規定しています。
古物商以外の者から古物の買い受け若しくは交換、または委託を受けて売買し、交換ができる場所は、古物商自らの営業所と取引の相手方の住所又は居所に限られるということになります。
行商との関連でいえば、自らの営業所以外の場所で買い受け、交換その他の古物取引をする場合には行商となります。行商をする場合は、行商しようとする者である旨が記載された許可申請書が提出されている必要があります。
「行商をしない」で許可申請書を提出している場合は、「行商をする」に変更の届出が必要をなります。
営業所の要件
独立性
営業所には独立性が保たれている必要があります。
具体的には、営業所が他の部屋と壁でしっかりと分けられているということです。営業所には古物台帳の保管義務があり、安全性の面から求められる要件と言えます。
そのため、シェアオフィスやコアワーキングスペースなどは独立性が確保できないことから、営業所としては認められません。
実在性
営業所の実在性とは、営業所としての実体があるということです。
バーチャルオフィスなど、事務所の住所を貸し出しているだけの実体のない事務所は営業所として認められません。
使用権原がある
営業所には、その申請者がその物件を古物営業として使用できる権利が必要です。
使用できる権利を証明する書類は、物件が自己所有か賃貸借かで違ってきます。
自己所有の場合、建物の登記簿謄本や税金の支払証明書などが証明書類となります。
賃貸借の場合、物件の賃貸借契約書の用途欄が「居住用」になっている場合は、家主からの使用承諾書が証明書類となります。
その他、物件が公営住宅の場合、居住用のみの貸し出しに決められているため使用権原は得られず、営業所としては認められません。
営業所の使用権原書類は、管轄警察署によって必要でない場合もあるため確認が必要です。
管理者の選任
古物営業法13条1項
古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
管理者は、店長のような営業所の業務責任者を指します。
管理者の要件として、未成年でないこと、欠格事由に該当しないこと、常勤性があることを満たす必要があります。管理者は古物商自身を選任することもできます。
帳簿等の保存
古物営業法16条から18条において取引の記録義務、帳簿等の備え付け義務について規定されています。
古物商は、古物取引を行う都度、「取引の年月日」「古物の品目及び数量」「古物の特徴」「相手方の住所、氏名、職業及び年齢」「相手方の確認のためにとった措置」を帳簿等に記載しなければなりません。
その古物取引を記載した帳簿等を、最終の記載をした日から3年間営業所に保存しておかなけらばなりません。
標識の掲示
古物営業法12条1項
古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
営業所には、公衆の見やすい場所に、決められた様式に従った標識を掲示する必要があります。
標識(古物商プレート)については、こちらの記事で確認してください。